
境内に足を踏み入れると、うっそうと生い茂る青々とした木々と重厚感あふれる社殿が目に飛び込んできます。
外冦に際して壱岐に、本宮八幡神社、箱崎八幡神社、印鑰神社、聖母宮とともに勧請されたと伝わる白沙八幡神社は、元々、京都府に鎮座する石清水八幡宮からの勧請により誕生した神社で、長らく海神の娘である玉依姫命を祭る海神社として、「筒城宮」や「管城宮」の名で島民に親しまれてきました。
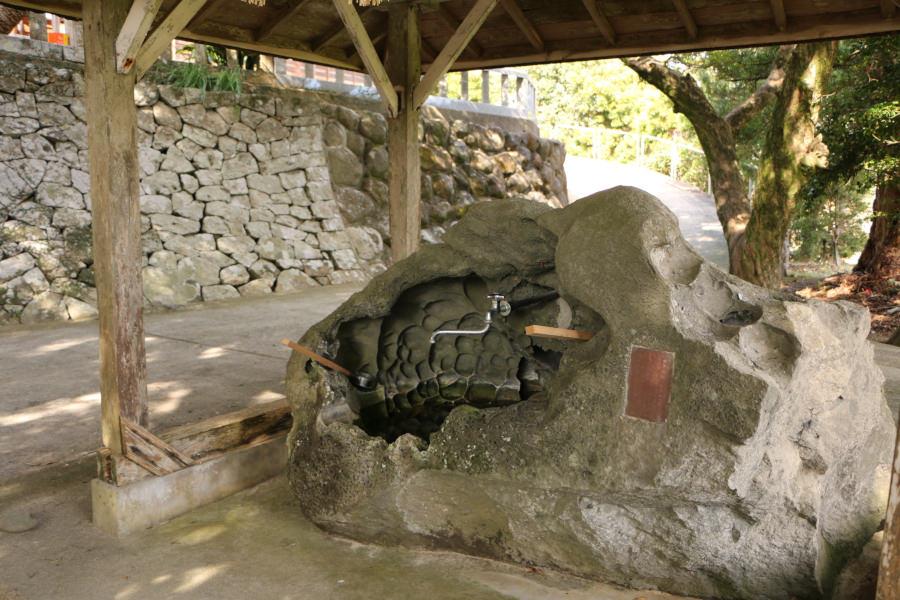
大分県の宇佐神宮からの勧請によって、現在の名前に変更となりましたが、漁業で繁栄してきた壱岐の人々に古くから愛されてきた神社のひとつであり、島内で格式高い神社のひとつです。海上安全や、良縁、五穀豊穣、厄除けなどに御利益があるといわれています。
拝殿の天井に掲げられた江戸時代に第29代の平戸藩主であった松浦鎮信によって奉納された三十六歌仙の絵や、長崎県指定天然記念物に選ばれるほどの社叢(しゃそう)など、境内には見応えのあるスポットが点在しています。