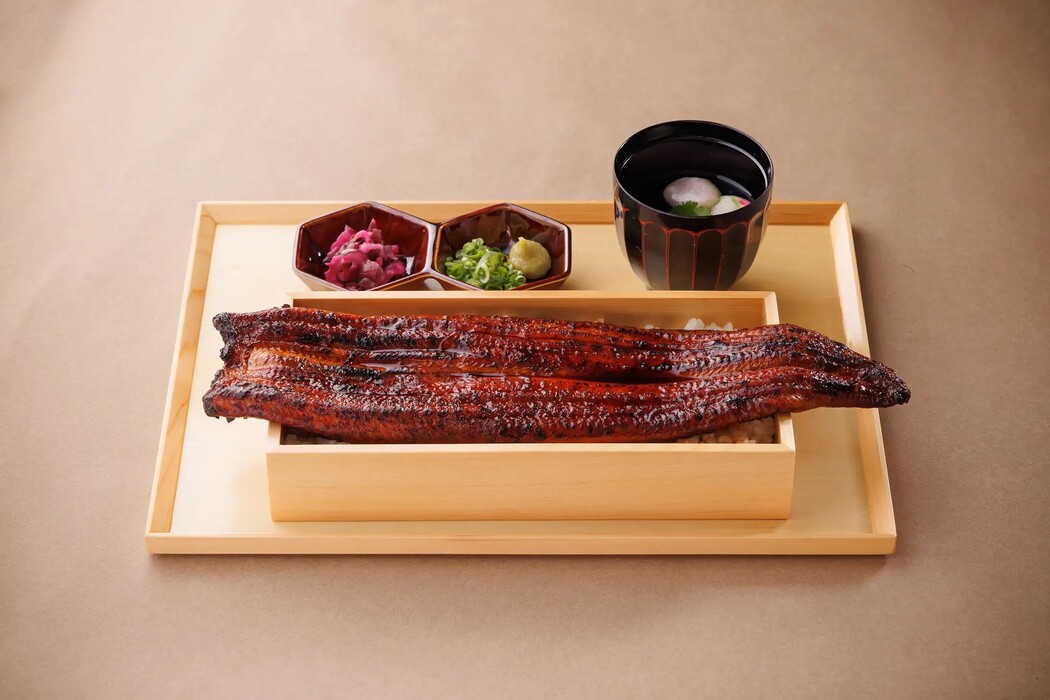諸堂を巡り、時を忘れる。家康公ゆかりの禅寺・袋井「可睡斎」へ
袋井市|【更新日】2024年2月21日

静岡県袋井市の可睡斎(かすいさい)は、火防の秋葉総本殿、曹洞宗の修行の場、そして徳川家康公ゆかりの禅寺と多彩な表情を見せ、広大な境内は見どころが満載。
この記事では境内の様子や、ご祈祷見学の貴重な体験をお伝えします。
目次
火防信仰の総本山、秋葉総本殿
600年の歴史を持つ曹洞宗の古刹
可睡斎は如仲天誾(じょちゅうてんぎん)禅師が室町時代の1401年に開山した禅寺。曹洞宗の僧堂で、今もたくさんの修行僧が修行をしています。
取材当日も、外のトイレを掃除する若いお坊さんを見かけました。可睡斎の広い敷地がとてもきれいなのは、お坊さん達のおかげなんですね。
秋葉三尺坊大権現様を祀る火防の霊場
御真殿に祀られる秋葉三尺坊大権現は、現在の長野県戸隠村に生まれ、新潟の三尺坊というお堂で修行。修行の末、火を自由自在に操る火生三昧の秘法を得ます。
護摩修行が満行を迎えた日に翼が生えたとされ、烏天狗の姿で表されるようになりました。
その後、白い狐に乗り、狐の止まったところを安住の地と定め、浜松市の秋葉山へ来たとされます。
御真体は明治の廃仏毀釈のときに秋葉山から可睡斎へと移され、今も大切にされています。
「三大誓願」をおこし「三毒の炎」を消す
三尺坊の三大誓願とは、火難を逃し、苦患を救い、満足を与えること。三毒の炎とは、「欲しい欲しいの貪りの心」、「憎い憎いの怒りの心」、「なんだかんだの愚痴の心」。
写真の御真言を7回繰り返すと、三毒の炎をはじめ、一切の障害がなくなり心からの願いが成就するといわれます。
現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら
「和尚、睡る可し」家康公と可睡斎の深い縁
「可睡斎」の名は家康公と和尚さんの逸話に由来
徳川家康公は、駿府、現在の静岡市の臨済寺で今川家の人質として少年時代を過ごしていました。若き日の可睡斎11代目住職は家康公の教育を受け持ったことがあり、愛知県の篠島に逃げる時にも協力した深いご縁が。
やがて時は過ぎ、浜松城主となった家康公は住職を招いて再会を喜びますが、住職は謁見中に居眠りしてしまいます。
怒る家臣たちに、家康公は「和尚にとって自分は子供のようなもの。だから安心して眠ってしまった。その親密な気持ちが嬉しい。和尚、睡るべし」と言い、そこから「可睡斎」と呼ばれるようになりました。
こちらの家康公と居眠り和尚さんのお人形は、袋井市の鈴木彦市さんが制作されたもの。高祖廟の隣に飾られていますので、ぜひ会いに行ってくださいね。
徳川家歴代将軍を祀る徳川家御霊屋
本堂にある徳川家御霊屋には、家康公と歴代将軍のご位牌が祀られています。
また、建物の屋根瓦など各所に葵の御紋が。宝物殿には徳川家から拝領した品々の一部が展示されていますので、そちらもぜひご覧ください。
武田勢から家康公を守った「出世六の字穴」
こちらは武田勢の遠州侵攻で追われた家康公が逃げ込み、命拾いしたと伝わる洞窟。
その後、家康公は天下統一を成し遂げる大出世をしたことから、出世六の字穴と呼ばれるようになりました。なお、「六の字」とは6つの観音様から名付けられたといわれています。
リズミカルな太鼓、迫力ある読経に異空間に誘われる
お勤めの見学もできる御真殿
こちらの御真殿では火災消除や家内安全、心願成就のご祈祷を受けることができます。ご祈祷時間は午前・午後3回ずつ。ご希望の方は事前にご予約ください。
また、拝観志納金を納めて寺院内を拝観される方は、昼と夕方のお勤めを見学することができます。今回、そっとご祈祷を見学させていただきました。
迫力あるご祈祷、気持ちがすっきり
実は私、ご祈祷を受けた経験がありません。御真殿の荘厳な雰囲気や、思ったより大人数のお坊さんに驚き、始まる前から緊張気味。
ご祈祷が始まると、リズミカルな祈祷太鼓の音、朗々とした大勢の読経の声、アコーディオンのような折り本の経典を空中で翻す転読の動作。その迫力にすっかり呑み込まれてしまいました。
お経の意味はわかりませんが、その音に魅了され、ご祈祷が終わる頃にはなぜか気持ちがすっきりしていました。
現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら
見どころ満載、諸堂を巡る
金色の天蓋に眼を奪われる本堂
こちらは本堂、御本尊の聖観世音菩薩が祀られている須弥壇の前です。金色の大きな天蓋に目を奪われ、口を開けてぼーっと見上げてしまいました。
この写真の中にも葵の御紋をいくつか見つけることができますね。お勤めはこちらで朝昼夕、365日行われます。
今も修行の場、坐禅堂
こちらの坐禅堂は今も修行の場として使われています。「立って半畳、寝て一畳」の言葉のとおり、一畳に布団を敷いて眠り、食事も坐禅も決められた場所で行います。
なお、一般の方も坐禅体験が可能。日帰りと宿泊があり、宿泊の場合は朝5時に修行僧の方と一緒に坐禅体験することができます。
見事なしつらえの瑞龍閣、ひなまつりのメイン会場
こちらは瑞龍閣、元旦から3ヶ月間開催される「可睡斎ひなまつり」のメイン会場にもなります。
国の登録有形文化財に指定された総ヒノキ造の建物は、天井絵や襖絵も見事。おひなさまに負けない華やかさです。
国登録有形文化財のお手洗い「大東司」
1937年に建築された水洗式トイレ
「東司(とうす)」とはトイレのこと。こちらは1937年、昭和12年に建築された水洗トイレです。
できてから90年ほど使われていますが、ちり一つなくとても清潔。もちろん匂いも全くしません。大東司も国の登録有形文化財に指定されています。
東司の神様、烏蒭沙摩明王
中央に立つのは烏蒭沙摩(うすさま)明王、高村晴雲の作です。炎の力でこの世の汚れを燃やし尽くす「トイレの神様」。
大東司がきれいなのは、明王様が睨みをきかせているからなのでしょうか。
清々しい空気に満たされた祈りの場で自分と向き合う
10万坪の敷地に25棟もの建造物がある可睡斎。歴史ある建物が多いのですが、屋外・屋内どこを見ても手入れや掃除が行き届き、清々しい空気に満たされています。
神聖な修行の場でありながら、坐禅体験やお勤めの見学など、広く一般の方にも開かれているところも魅力。
自分と向き合う時間を作りに、可睡斎を訪れてみませんか?
可睡斎へのアクセス
-
【住所】静岡県袋井市久能2915-1
【諸堂拝観料】700円(小学生以下無料)
※諸堂以外の境内見学は無料です
【駐車場】周辺の民間駐車場を利用
【公式サイト】https://www.kasuisai.or.jp/
※掲載時の情報です。最新の情報は公式サイトをご覧ください。